学群・専攻
経済学専攻
人・もの・お金の流れが、
暮らしにどう関係しているのかを学ぶのが経済学。
「行政・金融ユニット」では、
人とお金をつないで地域を設計できる力を、
「食・観光ユニット」では、地域の真の良さを理解し、
北海道内外の人々に価値あるものと
サービスを提供する力を身につけます。

経済学専攻は
こんな人におすすめ
- 01
- 自治体などで地域の活性化に貢献したい
- 02
- 北海道ならではの食や観光に興味がある
- 03
- お金の流れや投資について知りたい
学びのポイント
-
就職試験に向けた知識
主に、公務員や銀行員をめざす上で必要とされる、経済学の基礎力と応用力をしっかり修得していきます。
-
企画する力と調整する力
「行政・金融ユニット」では、地域住民との触れ合いを通して、そこに関わる人々を結びつける企画力や調整する力を身につけます。
-
食×農×観光
「食・観光ユニット」では、食×農×観光をめぐるさまざまな知識を修得するほか、実践体験を通して北海道経済の魅力を引き出す力を養います。
4年間の学び
必修科目 選択科目
| 項目 | 1年 | 2年 | 3年・4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基盤 教育科目 |
基盤教育科目
|
||||
| ゼミナール |
入門演習
基礎演習 |
ゼミナールI
ゼミナールII
|
ゼミナールIII
ゼミナールIV
ゼミナールV ゼミナールVI |
||
| 行政・金融 ユニット |
経済学のための数学・統計学
業界研究(金融) 金融リテラシー |
業界研究(行政) 金融業界演習 ファイナンス 環境金融論
不動産の経済分析
ミクロ経済学Ⅰ ミクロ経済学Ⅱ
応用ミクロ経済学
マクロ経済学Ⅰ マクロ経済学Ⅱ
応用マクロ経済学
|
地方財政論
地域金融論
金融史
金融とデータ分析
国際経済学
|
||
| 共通 |
|
計量経済学Ⅰ
計量経済学Ⅱ 経済史 地域・都市立地論 |
経済学史
開発経済論
地域経済学
北海道近現代史
日本経済事情
海外経済事情
|
||
| 食・観光 ユニット |
食・観光入門
北海道食・農業概論 北海道アウトドア概論 北海道観光概論 地域経済演習(観光) 地域経済演習(食・調理) 業界研究(食・観光・小売) 情報発信演習 |
食とSDGs
フードシステム論 食・観光の交流史 観光経済学 グリーン・ツーリズム論 宿泊業界演習 旅行業界演習 地域経済演習(食・農) |
農業経済論
札幌学(食文化) 観光とSDGs 札幌学(観光) 観光とデータ分析 交通業界演習 |
||
学びの特徴
その手段が経済学の学びです!

-
金融リテラシーを学ぶ お金は、社会で生きていく上で切っても切れない関係にあります。しかし、世の中には「お金のことを考えるのは苦手で…」という人が少なくありません。おかしなもうけ話に乗せられて、大損してしまう人も多いのが現実です。
お金に関して自分を守る知恵、お金と社会の仕組みについての知識、そして将来の豊かな生き方を実現していく学びを「金融リテラシー」と呼びます。サツダイではこれらを学べる科目を1年次から用意。できるだけ早い段階で学ぶことをすすめています。

-
「食・観光入門」で学ぶ 雄大な自然、四季折々の美しい風景、各地で育まれてきた食文化などが魅力としてあげられる北海道。実は、まだまだ知られていないこともたくさんあります。
「食・観光入門」は、食と観光について学ぶための導入科目です。北海道の食材や食文化、フード・ツーリズムやグリーン・ツーリズム、観光と経済・交通・SDGsの関連性、北海道庁が推進するアドベンチャー・ツーリズムなど、さまざまな視点から北海道の食と観光を取り上げていきます。
進路イメージ
また大学院への進学もあります。公務員試験対策のサポート体制もしっかりしています。
取得できる資格
めざす資格
●国内旅行業務取扱管理者
●ERE経済学検定試験
●ファイナンシャル・プランニング技能検定
●証券アナリスト試験
●宅地建物取引士
●ITパスポート試験
●公認会計士・税理士
めざす進路
〈民間企業〉
●金融業、「食・観光」関連産業(旅行、宿泊、航空、飲食、農業、食品、アウトドア、サービス)
〈公務員〉
●国家公務員(総合職、一般職)、北海道職員、市町村職員、北海道警察、警視庁など
●大学院進学・海外留学
卒業後の進路
- 内定先
- 北海道庁
農業土木職員 内定 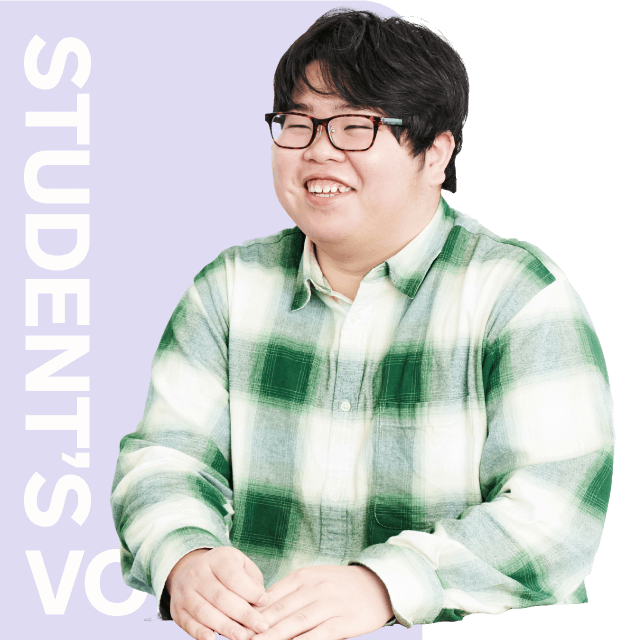
学位授与の方針
[ディプロマ・ポリシー:DP]
教育課程編成・実施の方針
[カリキュラム・ポリシー:CP]
教育課程編成の目的
経済学専攻では、経済分野の課題に対して、理論・応用についての知識と技能から地域における解決策を提示できる人材を育成する。
学修過程(分類毎の履修の目的・目標・過程)
- 〈1〉行政・金融系科目
- 経済学の理論分野および応用分野について深い知識と現実経済についてのデータ分析力を有し、行政・金融分野で求められる地域のヒトとおカネをつなげて課題解決できる人材を育てる。
- 〈2〉食・観光系科目
- 食・農業・観光等をめぐる知識と課題分析の技能を有し、実践体験を重視した学びを通じて、地域の産業や組織において率先して行動しそれぞれの分野の発展に貢献できる人材を育てる。
- 〈3〉地域創生系科目
- 経済学や関連分野の知識や技能を基に、実践体験を重視した学びを通じて、地域の魅力をより輝かせる解決策を見出すことができる人材を育てる。
- 〈4〉データ分析系科目
- 地域経済や地域産業の課題の分析に必要な統計データ・情報を収集し、データ分析の方法に基づいて課題を客観的にかつ正確に評価し、データに基づく解決策を提示できる人材を育てる。
- 〈5〉学際系科目
- 経済学と合わせ、経営・歴史・地理など隣接する学問分野の習得により、複眼的なアプローチと多様性への理解に基づいた地域課題の解決策を提示できる人材を育てる。
- 〈6〉ゼミナール科目
- 未知の経済課題に挑戦し、課題の正しい理解とよりよい解決策を自力で考案し、情報発信に結びつけることができる人材を育てる。
教育課程の構成と学習成果(DP)との関係
副専攻科目
経済学専攻を副専攻と認定する場合の条件は以下のとおり。
(1)以下に示す表の科目群から合計20単位以上を修得。
(2)科目群Ⅰから12単位以上を修得。
(3)科目群Ⅱから8単位以上を修得。
| 科目名(単位) | |||
|---|---|---|---|
| 科目群Ⅰ | マクロ経済学入門(2) ミクロ経済学入門(2) データ分析入門(2) 経済学のための数学・統計学(2) |
ミクロ経済学Ⅰ(2) ミクロ経済学Ⅱ(2) マクロ経済学Ⅰ(2) マクロ経済学Ⅱ(2) |
応用マクロ経済学(4) 応用ミクロ経済学(4) 計量経済学Ⅰ(2) 計量経済学Ⅱ(2) |
| 科目群Ⅱ | ファイナンス(4) 国際経済学(4) 地域金融論(4) 不動産の経済分析(2) |
金融とデータ分析(2) 地方財政論(4) 経済学史(4) 地域・都市立地論(2) |
地域経済学(4) 観光経済学(4)★ 農業経済論(4)★ 観光とデータ分析(2)★ |
★はみらい志向プログラムの指定科目
学修方法と評価
- 経済学の理論的枠組みの深い理解を、現実の経済問題に対して正確に応用する。
- 経済問題の解決策の探求にむけて、必要なデータの収集・分析ができる。
- 分析により得た知見を具体的な課題解決に結実するために、地域や組織との協同ができる。
- 各科目は、試験またはレポートにより100 点満点でAA~Eの6段階で評価し、60点以上を合格とする。
入学者受入れの方針
[アドミッション・ポリシー:AP]
札幌大学では、豊かな教養と確かな実践力を備え、他者と協力し、未来を切り拓き、地域や世界へはばたこうとする意欲的で多様な価値観をもつ学生を求めています。そのため、経済学専攻では、学力の3要素毎に以下のような資質・能力・意欲を持った人物を入学者として受け入れています。
経済学専攻 [入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)]については、以下のファイルをご確認ください。











